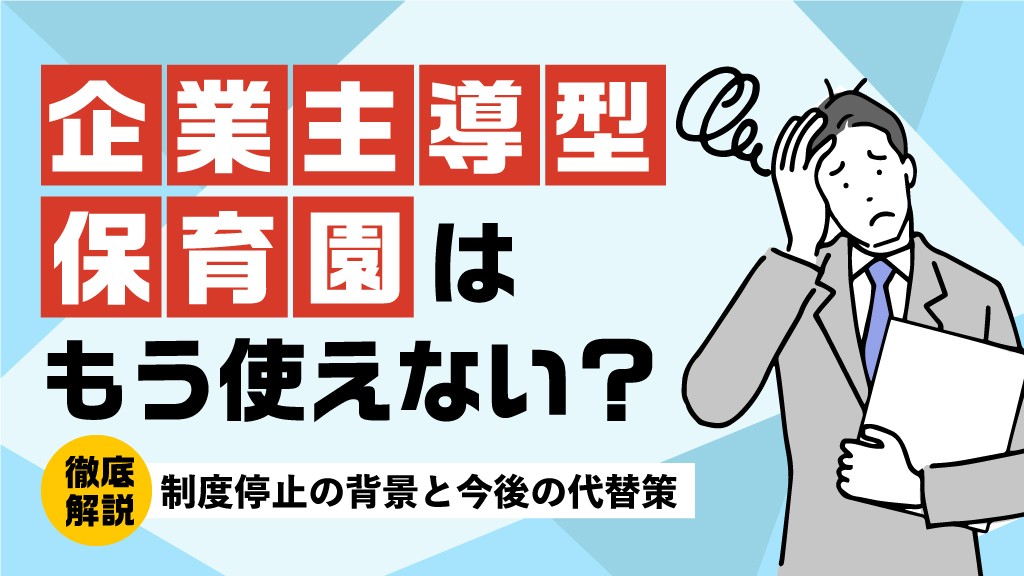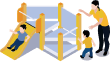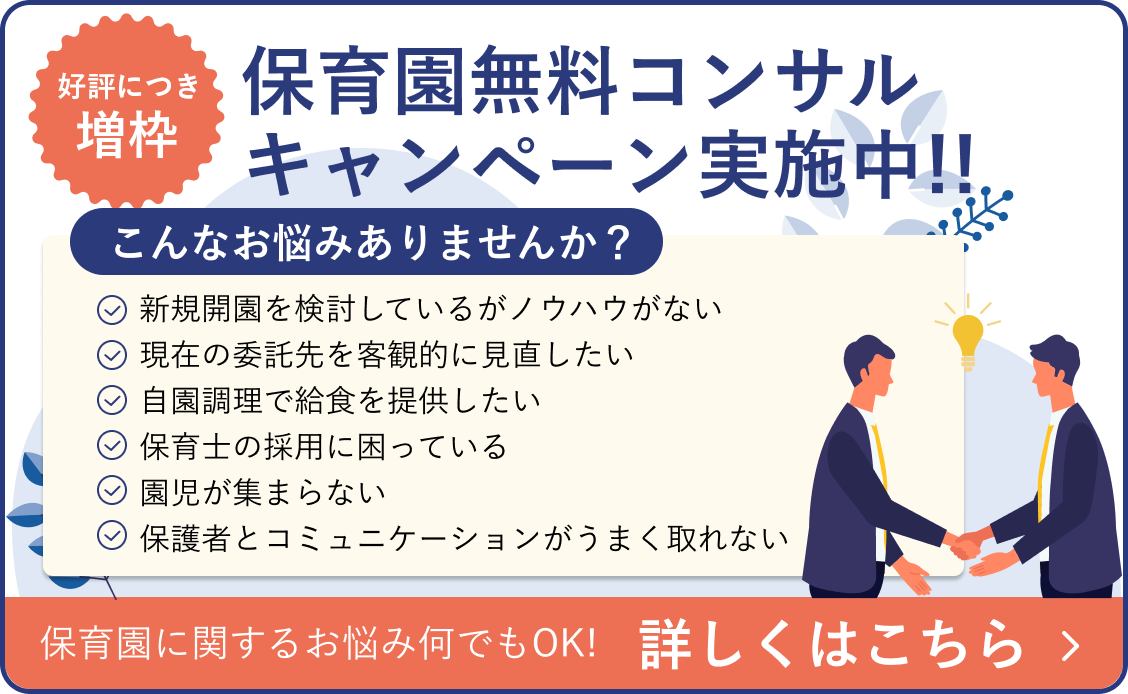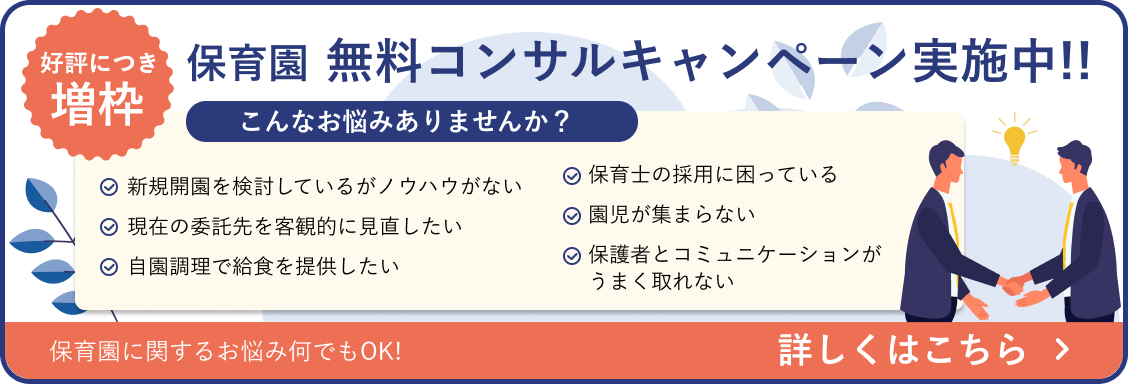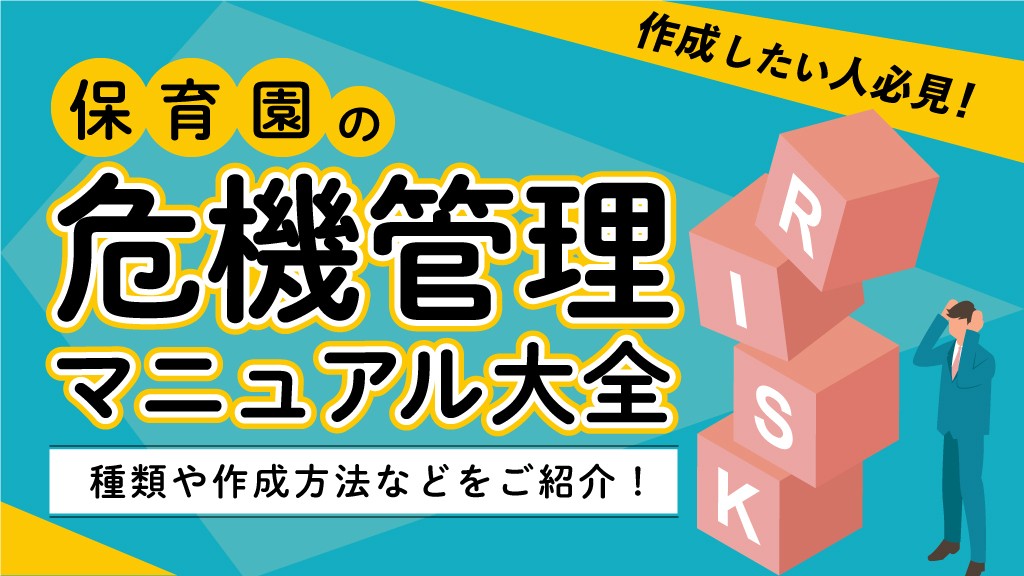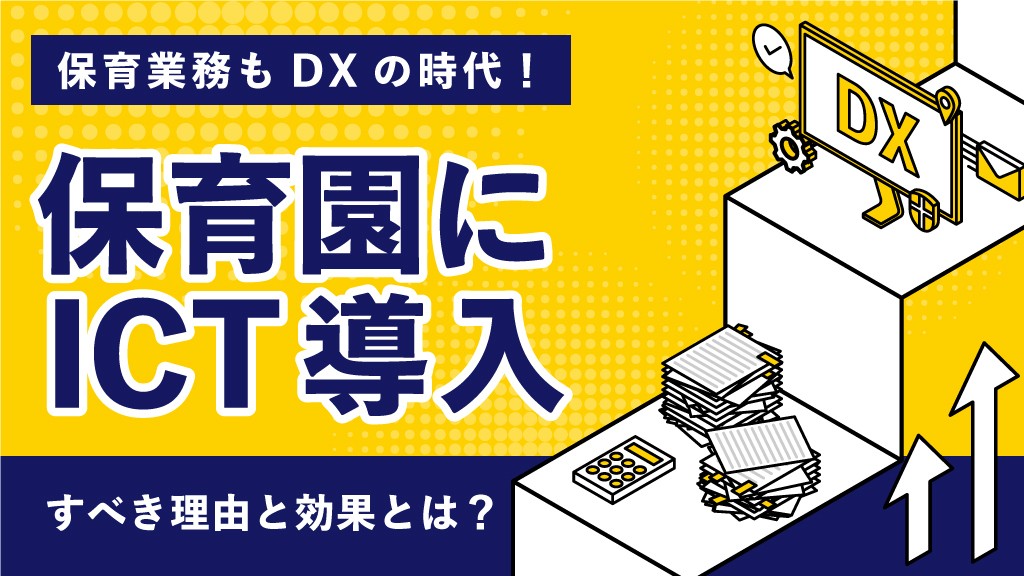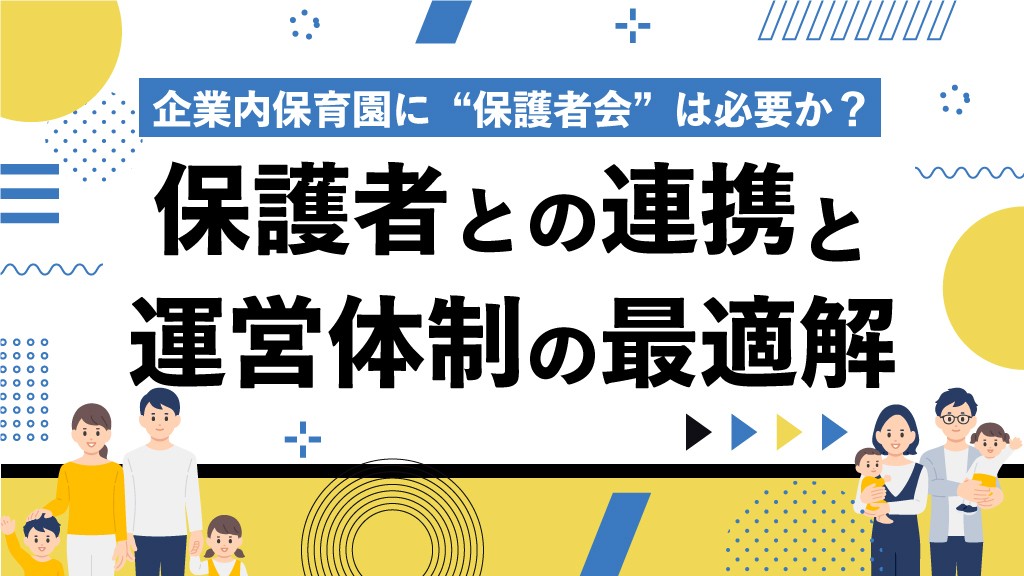企業主導型保育園はもう使えない?制度停止の背景と今後の代替策を徹底解説
「企業主導型保育園」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、企業が従業員の働き方にあわせた保育施設を設置できるよう、国が支援する制度です。
認可外施設に分類されながら、国の助成を受けられる点が画期的です。
目 次
- 1. 企業主導型保育園とは?制度の基本と特徴
- 1-1. 企業主導型保育園とはどんな制度?
- 1-2. 制度の目的と創設背景
- 1-3. 対象企業・補助の仕組み
- 2. 企業主導型保育園が“新規受付停止”になったのはなぜ?
- 2-1. 制度停止の概要
- 2-2. 制度が急拡大した結果、発生した問題
- 2-3. 今後の制度設計に向けた国の動き
- 3. 今から企業内に保育所を設けるなら、どんな選択肢がある?
- 3-1. 選択肢➀:認可外の事業所内保育所(企業内保育所)
- 3-2. 選択肢➁:認可保育園との連携
- 3-3. 選択肢➂:外部委託で保育園を運営
- 4. 企業主導型保育園から学ぶ、保育所設置のメリットとリスク
- 4-1. 得られたメリット
- 4-2. 補助金ありきの制度依存のリスク
- 5. 制度終了後も委託運営で企業内保育を実現
- 5-1. 委託運営を使えば制度外でも実現できる
- 5-2. 事例紹介:委託運営で成功した企業・病院
- 6. 【まとめ】企業・病院が今後検討すべき保育園運営の形とは?
- 6-1. 制度の「今」と「これから」を理解する
- 6-2. 保育園を“戦略的”に活用する視点を持つ
- 6-3. まずは自社の状況を相談できるパートナー探しを
- 7. 保育園運営の専門家に無料で相談

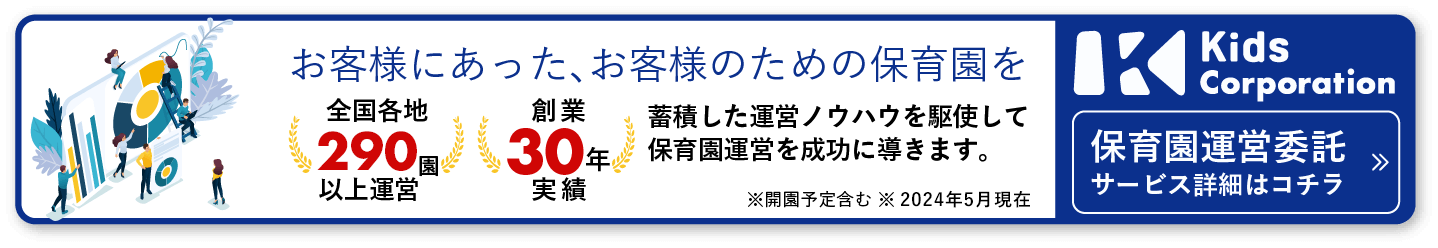
企業主導型保育園とは?制度の基本と特徴
企業主導型保育園とはどんな制度?
企業主導型保育園は、従業員の子どもを預かるための保育施設です。
認可外施設に分類されますが、一定の基準を満たすことで国の助成を受けられる点が大きな特徴でした。
また、自社の従業員だけでなく、地域の住民や他社の従業員の子どもも受け入れられる柔軟性も備えています。
制度の目的と創設背景
この制度は内閣府が主導し、2016年度からスタートしました。
その目的は、主に以下の2つです。
●待機児童問題の解消:
都市部を中心に深刻化していた待機児童問題を解決するためです。施設整備費から運営費までを補助する形で企業にも保育の受け皿を増やし、促すことを目的としています。
●女性の就労継続支援:
子育て中の女性が安心して働き続けられるよう、多様な働き方に対応した保育環境を整備することを目的としています。これにより、採用力の強化にもつながります。
対象企業・補助の仕組み
補助金の対象は中小企業が中心でしたが、大企業も利用できます。
施設の整備費や預かる歳児ごとに設定された運営費や処遇改善等の加算等含めた補助金が支給され、自治体の認可が不要なため、比較的スピーディーに開設できるという特徴がありました。
企業主導型保育園が"新規受付停止"になったのはなぜ?
制度停止の概要
「柔軟で助かる制度なのに、なぜ停止になったの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実は、企業主導型保育園は2023年から新規申請の受付が停止されています。
ただし、すでに運営している施設はそのまま継続が可能です。
新規申請停止の背景には、制度の運用におけるいくつかの課題がありました。
制度が急拡大した結果、発生した問題
制度が急拡大した結果、以下のような問題が浮上しました。
●監査、報告の不備が多発:
一部の運営法人で、国への監査や報告に不備が見られました。
●運営法人の質のばらつき:
施設の急増に伴い、運営事業者ごとの保育の質や安全性が不十分なケースも散見されました。
●行政側の監督体制が追いつかない現実:
監督官庁である内閣府の体制が十分でなく、多数の施設を十分に管理・監督しきれないという実情がありました。
また、少子化の想定以上の加速もあり、受け皿整備はよりピンポイントになっていくでしょう。
令和6年度の段階で、全国的な受け皿整備は概ね完了しています。
今後は、質を高める方向性にシフトしていく動きになります。
(参考文献:こども家庭庁 「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について)
今後の制度設計に向けた国の動き
これらの課題を受け、前述の通り今後は保育の質や安全性を重視する方向へ舵を切っています。
内閣府から厚生労働省への管轄移行や、「保育制度の一元化」に向けた議論も進められています。
今から企業内に保育所を設けるなら、どんな選択肢がある?
選択肢➀:認可外の事業所内保育所(企業内保育所)
企業の敷地内に小規模な保育所を独自に設置する方法です。
独自の運営基準を設ける必要がありますが、企業ごとのニーズに合わせた柔軟な運営が可能です。
認可園と違い特に縛りもない為、独自運営か、外部の専門事業者に委託するかを選択できます。
認可外であれば、自由度高く運営が可能な反面、運営費等の補助があまりなく、コスパを考えて本当に必要かを判断します。
選択肢➁:認可保育園との連携
単独での開設が難しい場合、自治体や既存の認可保育園と連携する選択肢もあります。
自治体との協定が前提となりますが、地域全体の待機児童対策に貢献できます。
また自治体により、地域型保育事業での認可設置の可能性もゼロではありません。
ハードルはかなり高いですが、各自治体に問い合わせてみるのも良いでしょう。
選択肢➂:外部委託で保育園を運営
保育園の開設・運営の専門事業者にすべてを委託する方法です。
保育のプロによる安定した運営が期待できます。
労務管理や保育士の採用、教育などを任せられるため、企業の負担が軽減されます。
初期の設計から日々の運営まで、一貫したサポートを受けられるのが大きなメリットです。
企業主導型保育園から学ぶ、保育所設置のメリットとリスク
得られたメリット
企業主導型保育園の成功事例からは、多くのメリットが見られました。
●採用強化:
子育て世代の応募が増え、優秀な人材の確保に繋がります。
●定着率向上:
復職しやすい環境が整うことで、従業員の離職を防ぎます。
●従業員満足度UP:
福利厚生としての魅力が高まり、従業員のエンゲージメントが向上します。
補助金ありきの制度依存のリスク
一方で、補助金に頼りすぎた制度設計にはリスクも伴います。
制度が突然変更されると、運営や経営安定の面で大きな影響が出る可能性があります。
今後は補助制度の有無や内容に左右されない、"持続可能なモデル"を構築することが求められます。
制度終了後も委託運営で企業内保育を実現
委託運営を使えば制度外でも実現できる
企業主導型保育園の制度が終了しても、委託運営という形で(もちろん直営も)企業内保育を実現することは可能です。
●運営ノウハウの蓄積を活かす:
専門事業者の長年のノウハウを活用することで、質の高い保育を安定的に提供できます。
●保育士確保・運営管理の効率化:
保育士不足が深刻化する中で、採用や日々の労務管理を専門家に任せることで、企業の負担を大幅に軽減できます。
事例紹介:委託運営で成功した企業・病院
医療機関が夜勤に対応した保育園を外部委託で開設した事例があります。
多様なシフトに対応できる柔軟な受け入れ体制を構築でき、従業員の働きやすさが格段に向上しました。
夜勤等特殊な時間帯の勤務がある中、外部パートナーの継続的なサポートが成功の鍵となったケースです。
【まとめ】企業・病院が今後検討すべき保育園運営の形とは?
制度の「今」と「これから」を理解する
企業内保育園の導入を検討する際は、補助金だけに頼らない視点を持つことが重要です。
企業主導型保育事業の終了が示すように、国の制度は常に変化します。
そのため、補助制度の有無や内容に左右されない、持続可能な運営モデルを考える必要があります。
制度が変わっても、子育て世代の働き手にとっての保育ニーズがなくなるわけではありません。
むしろ、共働き世帯の増加に伴い、多様な保育の受け皿は今後も求められ続けるでしょう。
だからこそ、大切なのは自社の状況と将来像をしっかりと見つめ、自社に合った形を選ぶ必要性を理解することです。
福利厚生としてだけでなく、採用力や従業員定着率の向上といった経営戦略の一環として、保育施設をどのように活用していくかその答えは、企業ごとに異なります。
保育園を"戦略的"に活用する視点を持つ
●採用・定着・ブランディングの一環:
子育て世代の優秀な人材を惹きつけ、採用力を高めます。
また、育児と仕事の両立を支援することで、従業員の離職を防ぎ、定着率を向上させます。
●人事施策や働き方改革と連携させる:
フレックスタイム制やリモートワークといった働き方改革と連携させることで、従業員の多様なニーズに応えることができます。
●経営資源としての「保育」をとらえる:
保育園運営にかかるコストを、単なる費用ではなく、企業の成長を支えるための投資と捉えることです。
従業員のエンゲージメント向上や生産性の向上といった、長期的なリターンが期待できます。
まずは自社の状況を相談できるパートナー探しを
●制度動向や設計をアドバイスしてくれる存在:
刻々と変わる保育制度の動向や、最新の設計基準について専門的なアドバイスをしてくれるパートナーを見つけることが、失敗しない運営への第一歩です。
●委託による柔軟かつ安心な運営体制:
自社で運営体制をすべて整えるのは大きな負担です。
保育士の確保や日々の運営管理を専門事業者に委託することで、柔軟かつ安心な運営体制を実現できます。
●現在の課題と将来像を踏まえた伴走支援:
単に運営を委託するだけではなく、自社が抱える現在の課題や、将来のビジョンを共有し、共に解決策を考えてくれる「伴走者」として機能してくれるパートナーを選ぶことが重要です。
保育園運営の専門家に無料で相談
保育園運営に関わる会社・サービスは多く存在しますが、これから保育園の新設、委託切り替えを検討されている方はぜひキッズコーポレーションへご相談ください!
当社は全国356園以上の保育園を運営しており、病院様や企業様の保育園開設・運営を多数お手伝いさせていただいております。
そのノウハウを活かして「どの制度で開設すべきなのか」「失敗しない保育園開設の流れ」等、開設にあたってのアドバイスを無料で行なっております。
「気になるけどいきなり相談はちょっと…」という方は無料でダウンロードいただける資料をご確認ください。