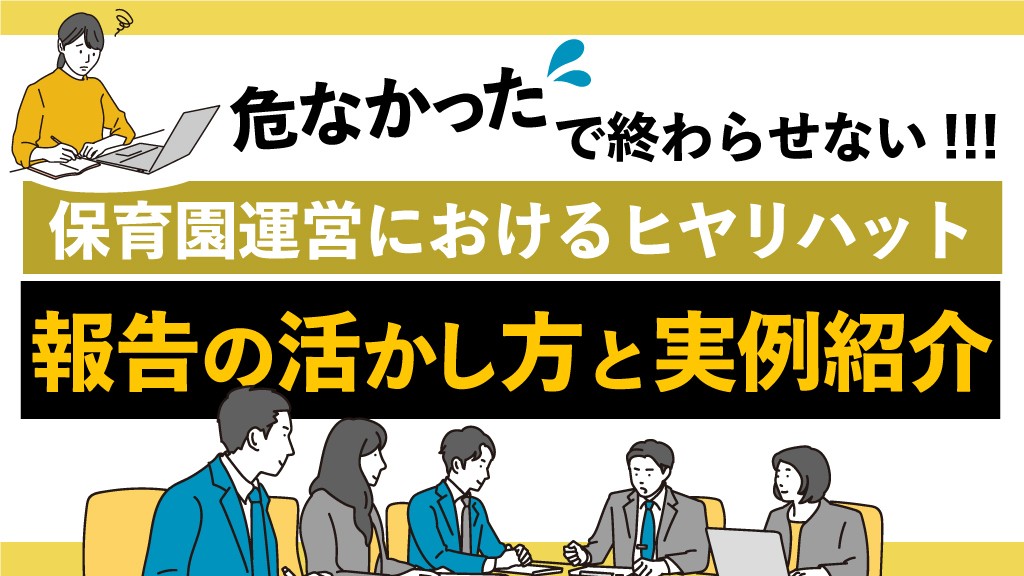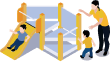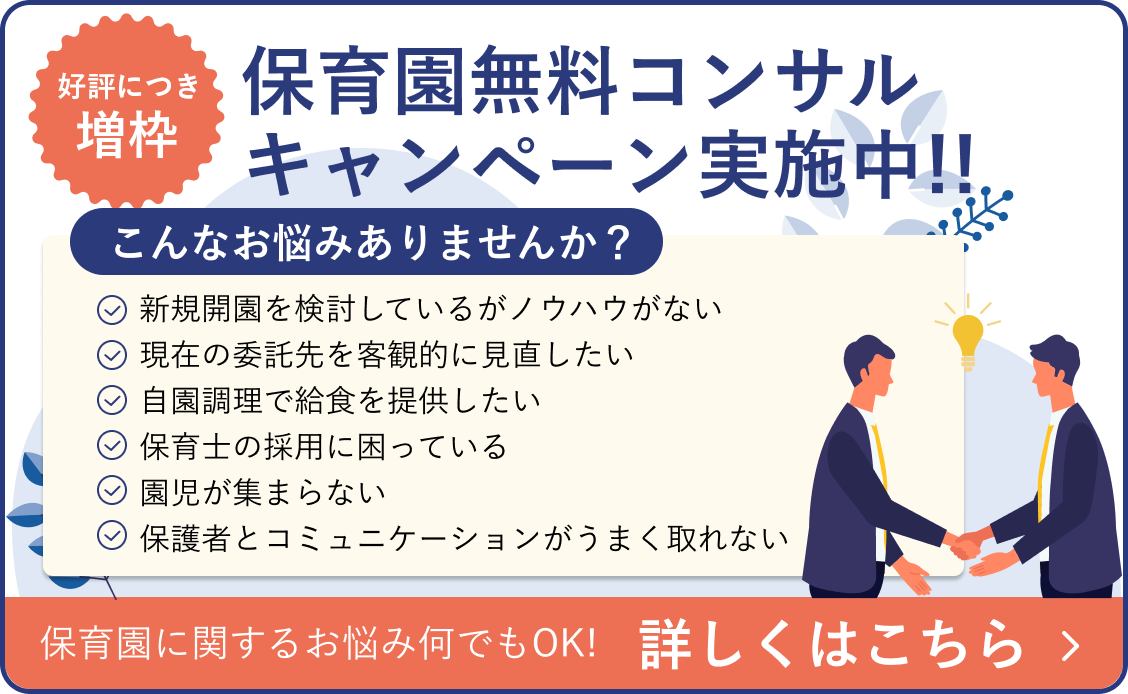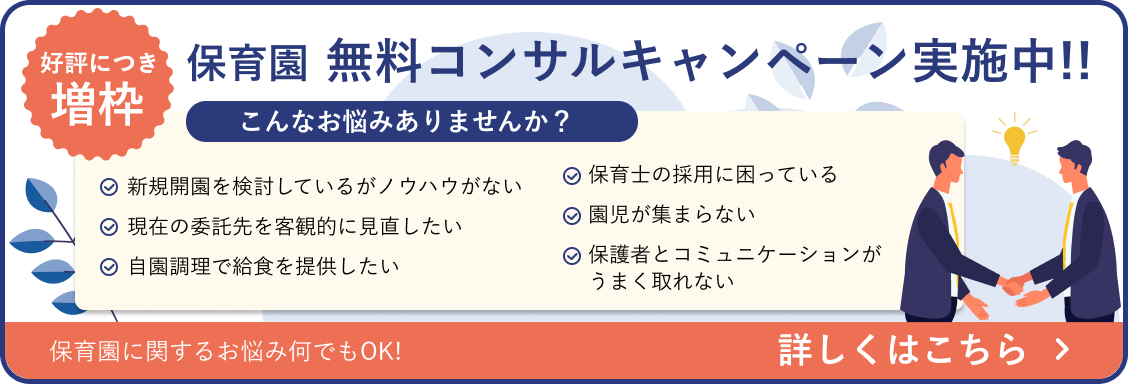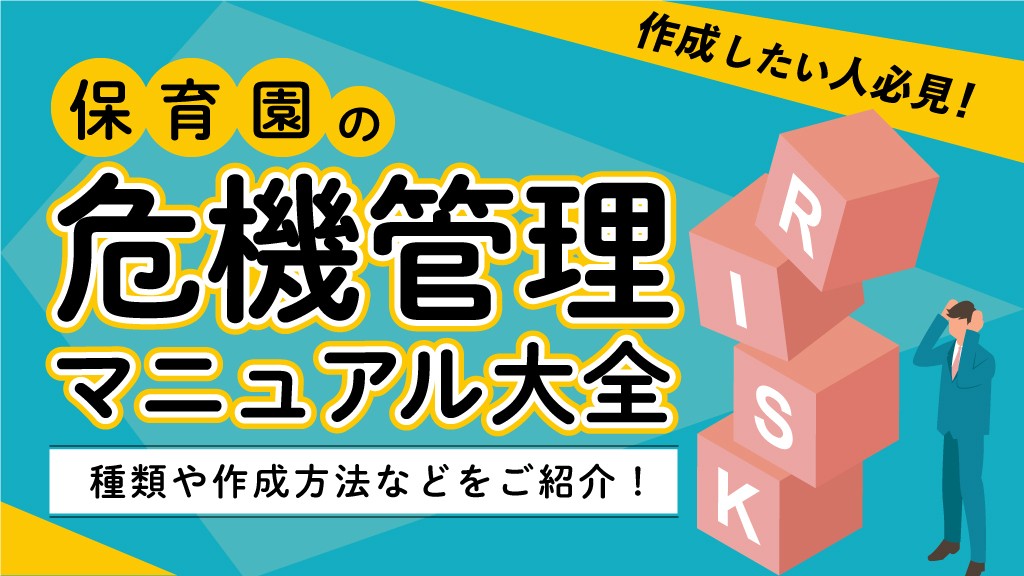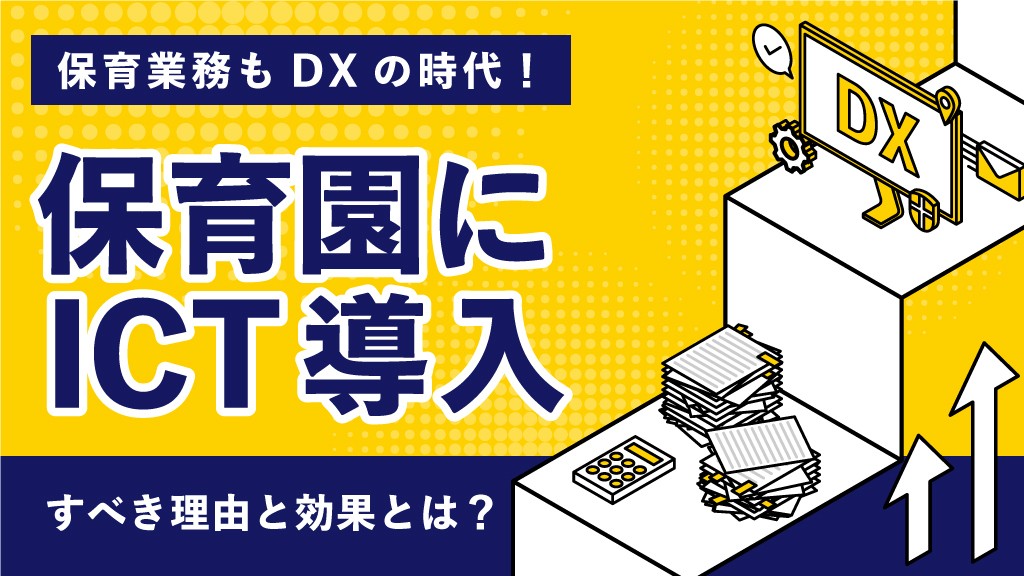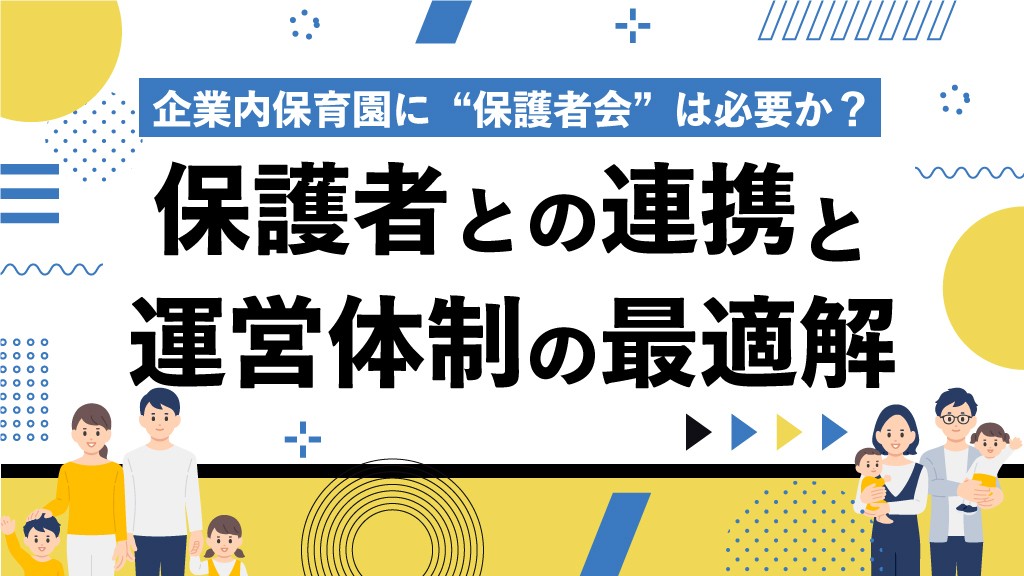「危なかった」で終わらせない!保育園運営におけるヒヤリハット報告の活かし方と実例紹介
保育園運営において、子どもたちの安全を確保することは最も重要な責務です。
「ヒヤリハット報告」を適切に分析し、再発防止策を講じることで、保育園全体の安全体制を強化し、子どもたちが安心して過ごせる環境を作りましょう。
目 次
- 1. ヒヤリハットとは?保育園における定義と重要性
- 1-1. ヒヤリハット=「事故の一歩手前」
- 1-2. 「事故ゼロ」だけでは不十分な理由
- 2. ヒヤリハットを「現場改善」に活かす運用のポイント
- 2-1. (1) 報告を「叱責の材料」にしない文化づくり
- 2-2. (2)ヒヤリハット→再発防止策→共有までがワンセット
- 2-3. (3) 委託・外部連携園では運営会社との情報共有も必須
- 3. 【事例紹介】実際にあったヒヤリハットと改善策
- 3-1. 事例(1):園庭での転倒→ルート見直しと動線設計改善
- 3-2. 事例(2):おやつの誤飲未遂→食事時のチェック体制強化
- 3-3. 事例(3):お迎え確認のミス→引き渡しフローの見直し
- 4. ヒヤリハット報告を浸透させるためにできること
- 4-1. 職員が「気軽に出せる」環境づくり
- 4-2. ICTツールを活用した記録・共有の効率化
- 5. 保育園運営の専門家に無料で相談

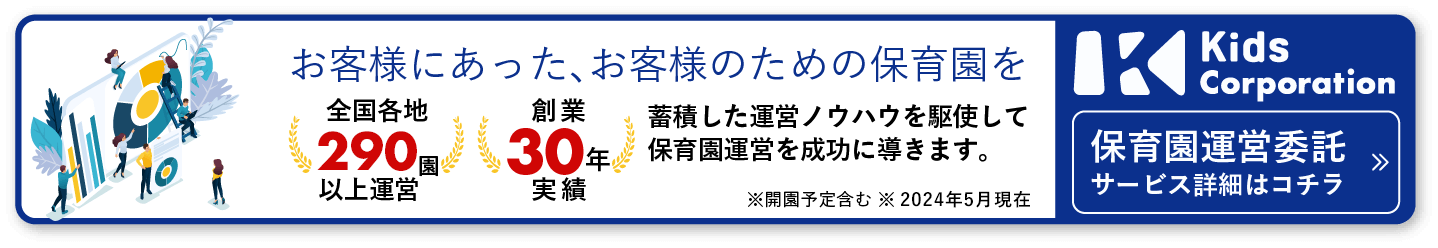
ヒヤリハットとは?保育園における定義と重要性
ヒヤリハット=「事故の一歩手前」
ヒヤリハットとは、文字通り「ヒヤリとした」「ハッとした」状況を指し、事故寸前の出来事と定義されます。
保育園における事例としては、園庭での転倒、誤飲しかけた、登園確認の行き違い等が挙げられます。
これらの事例は、結果として事故にはならなかったため軽視されがちですが、保護者からのクレームや、ひいては園の信頼失墜にも繋がりかねない"見逃せないサイン"です。
潜在的な危険因子が顕在化したものであり、看過することはできません。
「事故ゼロ」だけでは不十分な理由
「事故が起きなかったからといって、問題がないとは限らない」という認識を持つことが、安全管理において極めて重要です。
事故が起きなかった場合でも、その背後には必ず何らかの潜在的な危険が潜んでいるためです。
ヒヤリハットは、そのような危険を顕在化させる貴重な情報であり、小さな兆候を拾い、未然に防ぐことが園の信頼に繋がります。
ヒヤリハットを「現場改善」に活かす運用のポイント
(1) 報告を「叱責の材料」にしない文化づくり
ヒヤリハット報告を積極的に促す上で、最も重要な前提は、報告が個人の責任を追及したり、叱責したりするためのものではない、という共通認識を園全体で醸成することです。
園長や主任が率先して、報告された内容を個人のミスとしてではなく、組織全体の安全体制における改善点として受け止める姿勢を明確に示すことが大切です。
もし報告が個人の評価に悪影響を及ぼすと職員が感じれば、報告が滞り、貴重な情報が埋もれてしまいます。
また、報告への心理的なハードルを下げるために、書式や記録の形式を工夫して、書きやすさを担保することも重要です。
例えば、簡潔なチェックリスト形式にしたり、記述量を少なくしたりすることで、報告にかかる手間を減らし、気軽に提出できる環境を整えられます。
(2)ヒヤリハット→再発防止策→共有までがワンセット
ヒヤリハット報告は、単に「報告して終わり」ではなく、必ずフィードバックを返す仕組みにすることが重要です。
「ヒヤリハット→再発防止策→共有」のサイクルを確立することで、報告された情報が確実に現場改善に繋がっていることを職員が実感でき、報告のモチベーション向上にも繋がります。
以下のようなプロセスを踏むことで、個々のヒヤリハットが園全体の安全意識向上と具体的なリスク低減に繋がります。
●報告:職員がヒヤリハット事例を報告する
●分析:報告された内容を基に、何が原因で、どうすれば防げたのかを分析する
再発防止策の検討:分析結果に基づいて、具体的な改善策を立案する
●共有:検討された再発防止策を、定例会や朝礼などを活用して職員間で共有し、全員が同じ意識レベルで安全対策に取り組めるよう周知徹底する
(3) 委託・外部連携園では運営会社との情報共有も必須
特に、病院・企業内に設置された事業所内保育施設などの外部事業者に運営を委託している保育園においては、運営会社との密な情報共有が不可欠です。
運営会社は、受託園が適切な事故予防体制を構築・維持しているかを定期的にチェックする責任があり、ヒヤリハットの情報は、このチェックにおいて重要な指標となります。
また、ヒヤリハットの適切な報告と、それに基づく改善活動を共有することは、クライアント(病院・企業)との信頼関係維持にも影響します。
透明性の高い情報共有は、万一の事態に際しても、迅速かつ適切な対応に協力体制を築く上で極めて重要です。
【事例紹介】実際にあったヒヤリハットと改善策
事例(1):園庭での転倒→ルート見直しと動線設計改善
●発生状況:
園庭で遊んでいた園児が、地面に放置されていた小石やわずかな段差につまずきそうになった事例です。
幸い転倒には至らずケガもありませんでしたが、一歩間違えれば、顔や頭を打つなどの重大なケガに繋がる可能性がありました。
●問題点:
小石や段差の危険が放置されていたため、安全な遊び場としての管理が不十分でした。
以下の改善策を実施し、同様の事例が減少しました。
(1)園庭全体を詳細に点検し、危険な小石や段差のある場所を特定。
(2)子どもたちの主要な遊びのルートや動線を見直し、危険箇所を避けるように再設計。
(3)危険箇所への子どもの立ち入りを制限するため、職員の配置を調整し、監視体制を強化。
(4)定期的な園庭の清掃と点検のルーティンを確立し、安全な状態を維持することを徹底。
事例(2):おやつの誤飲未遂→食事時のチェック体制強化
●発生状況:
おやつの時間、年齢に合わないおやつが一部園児に提供されそうになった事例です。
保育士が直前に気づき、提供を中止したため誤飲することはありませんでした。
●問題点:
おやつの準備や提供において、園児個々のアレルギーや月齢・年齢に応じた配慮が十分に徹底されていませんでした。
以下の改善策を実施し、同様の事例が減少しました。
(1)全園児のアレルギー・形状・誤飲リスクを一覧化した資料を作成し、厨房と保育室の分かりやすい場所に掲示。
(2)おやつ提供前のダブルチェック体制を導入し、担当保育士と別の職員が、園児個々のアレルギー、適切な形状、誤飲リスクの有無を必ず確認するよう義務付けた。
(3)全職員を対象に誤飲防止に関する再教育を実施し、特に乳幼児期の咀嚼能力の発達段階や、誤嚥のリスクについて理解を深めた。
事例(3):お迎え確認のミス→引き渡しフローの見直し
●発生状況:
降園時、別保護者への引き渡し寸前で気づいたケースです。
幸い、引き渡し寸前で保育士が間違いに気づき、事故には至りませんでした。
●問題点:
保護者の顔と名前の一致確認、登園時の情報との照合が徹底されておらず、引き渡し時の確認フローに不備がありました。
人為的なミスが発生しやすい状況でした。
以下の改善策を実施し、同様の事例が減少しました。
(1)園児の登録情報のデジタル化し、保護者の顔写真、連絡先、緊急連絡先などを一元的に管理できるシステムを導入しました。
(2)お迎え時のダブルチェック体制を導入しました。具体的には、園児を引き渡す担当保育士と、それを確認する別の職員の2名体制で、保護者の身分証明書や登録情報との厳密な照合を徹底しました。
(3)登降園管理システムを導入し、ICカードやQRコードを利用した、より確実な本人確認を行うようにしました。
これにより、視覚だけでなくシステム的な認証も加わることで、ミスの発生を抑制しました。
ヒヤリハット報告を浸透させるためにできること
職員が「気軽に出せる」環境づくり
ヒヤリハット報告の活性化には、職員が報告することへの心理的な抵抗を感じさせない「心理的安全性」の高い環境が不可欠です。
そのために、匿名報告の導入や"軽微なミスもOK"な風土整備、新人・ベテラン問わず、全員が参加できる運用方法を構築することが重要です。
これにより、問題が大きくなる前に潜在的な危険を早期に発見できます。
ICTツールを活用した記録・共有の効率化
ヒヤリハット報告の運用を効率化し、報告から改善までのサイクルをよりスムーズにするためには、ICTツールの活用が非常に有効です。
従来の紙媒体での報告は、集計や分析に手間がかかるだけでなく、情報の共有にも時間がかかるため、紙ではなくアプリやクラウドを使う園も増加しています。
また、報告されたヒヤリハット情報をリアルタイムで集計し、発生頻度、場所、時間帯、具体的な内容などの傾向を自動的に分析することが可能になります。
これにより、特定の事象に集中してヒヤリハットが発生しているといった傾向を素早く把握し、効果的な改善策を講じることができます。
さらに、分析結果や改善策を園内の職員間で迅速に共有することも容易になり、一連のプロセスを自動化・効率化することができます。
保育園運営の専門家に無料で相談
保育園運営に関わる会社・サービスは多く存在しますが、これから保育園の新設、委託切り替えを検討されている方はぜひキッズコーポレーションへご相談ください!
当社は全国356園(2025年4月1日時点)の保育園を運営しており、病院様や企業様の保育園開設・運営を多数お手伝いさせていただいております。
そのノウハウを活かして「どの制度で開設すべきなのか」「失敗しない保育園開設の流れ」等、開設にあたってのアドバイスを無料で行なっております。
「気になるけどいきなり相談はちょっと…」という方は無料でダウンロードいただける資料をご確認ください。